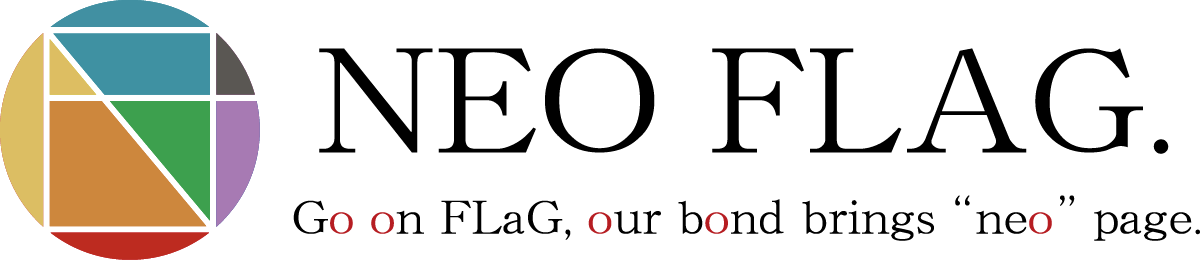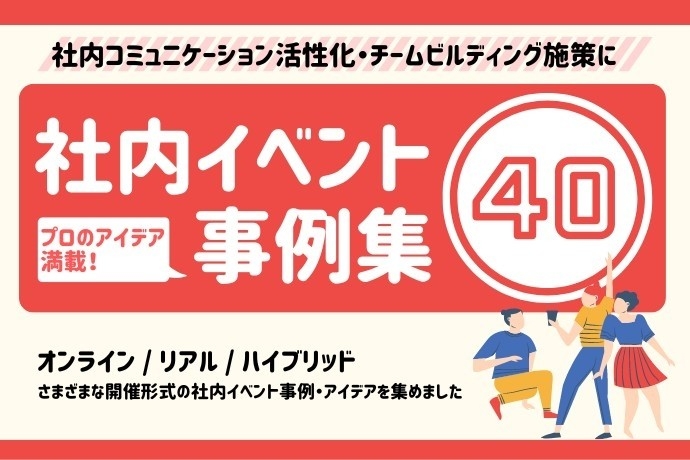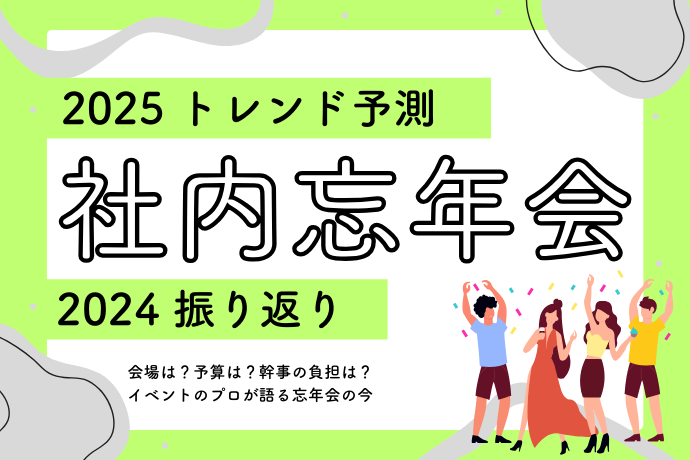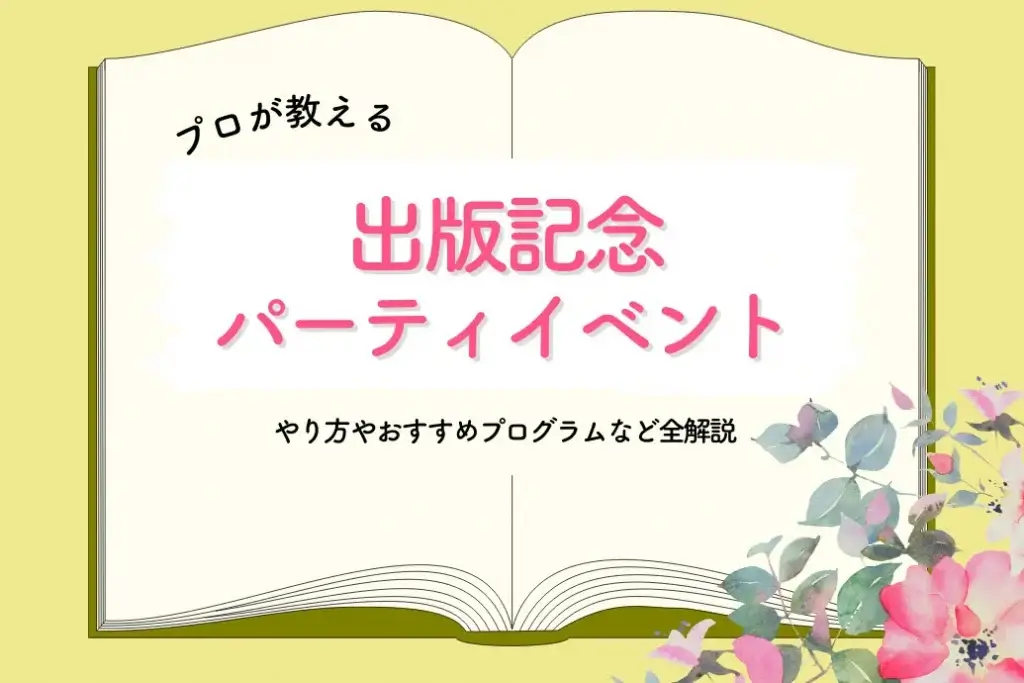こんにちは! 法人パーティープロデュースの「NEO FLAG.」です。
年末年始が近づくと、多くの企業で「新年会」の企画が始まります。しかし、初めて幹事を任された方の中には、「新年会って具体的に何をする会?」「いつ開催すればちょうどいいの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
新年会は、単なる飲み会ではありません。新しい年の始まりに、社員同士の絆を深め、今年一年の目標を共有する大切な場です。
本記事では、新年会の基本的な意味や目的、開催時期から具体的な企画のポイントまで、幹事の皆様に役立つ情報を詳しくご紹介します。社内イベントの企画・運営に携わる総務・人事の方は、ぜひ参考にしてくださいね◎
新年会ならイベントプロデュースのNEO FLAG.におまかせください

当社では、コミュニケーションを活性化させるイベント関連サービスを複数展開しています。開催形式もオンライン・リアル・ハイブリッドなど、あらゆる形式に対応OK。これまで入社式や周年記念パーティーなど、さまざまな規模のイベントを合計2000件以上手がけてまいりました。
新年会などの社内イベントでも多くの企業・団体様にご利用いただいています。
そのため多種多様なイベントのノウハウも豊富です。新年会のプログラムや演出/進行アイデアなら、当社におまかせください。一般的なイベント運営マニュアルにはない、プロの視点からお客様のお悩みを解決します。ぜひご相談くださいね。
新年会とは?基本的な意味を理解しよう
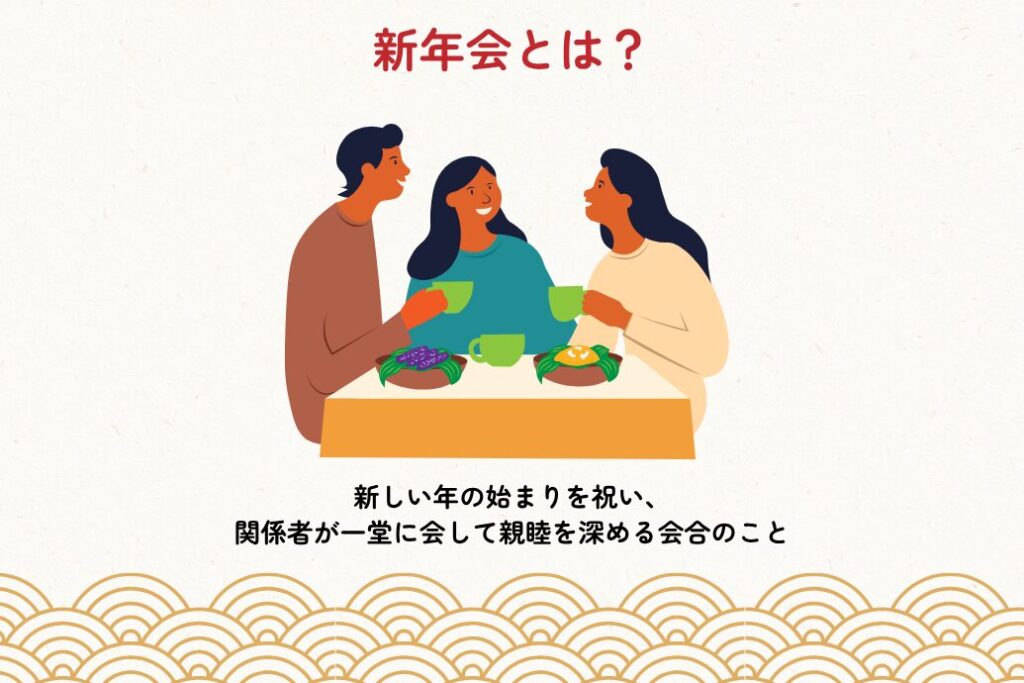
新年会について正しく理解するためには、まずその定義と歴史的背景を知ることが大切です。
新年会の定義と由来
新年会とは、新しい年の始まりを祝い、関係者が一堂に会して親睦を深める会合のこと。
企業や団体においては、年明けに社員や取引先などを集めて開催される懇親会として位置づけられています。
日本における新年会の文化は、古くから続く「年始の挨拶回り」や「新年の宴」という習慣に由来していて、江戸時代には商家が年始に番頭や奉公人を集めて酒宴を開く風習があり、これが現代の企業の新年会の原型となったと言われています。
現代の企業における新年会は、単に新年を祝うだけでなく、組織の一体感を醸成し、新しい年の目標や方針を共有する場としての役割も担っています。経営層から社員へのメッセージを伝える機会であると同時に、普段は異なる部署で働く社員同士が交流できる貴重な時間でもあるのです。
新年会と他の社内イベント(忘年会・賀詞交換会など)との違い
新年会と混同されやすい社内イベントとして、忘年会や賀詞交換会があります。
忘年会は文字通り「年を忘れる会」であり、その年の苦労や大変だったことを忘れ、リフレッシュすることが主な目的。
開催時期は12月で、一年の締めくくりとしての意味合いが強い行事です。
一方、新年会は「新しい年を迎える」ことが主眼です。過去を振り返るのではなく、未来に向けた抱負や目標を語り合い、前向きなエネルギーを共有する場となります。忘年会が「締めくくり」なら、新年会は「スタート」を切るためのイベントと言えますね。
賀詞交換会は、より フォーマルな新年の挨拶の場です。主に取引先や業界関係者など、社外の方々を招いて開催されることが多く、名刺交換や挨拶が中心となります。新年会は賀詞交換会と比べると、社内の親睦を深めることに重きを置いているため、よりカジュアルで長時間の開催となることが多いです。
新年会を開催する目的とは
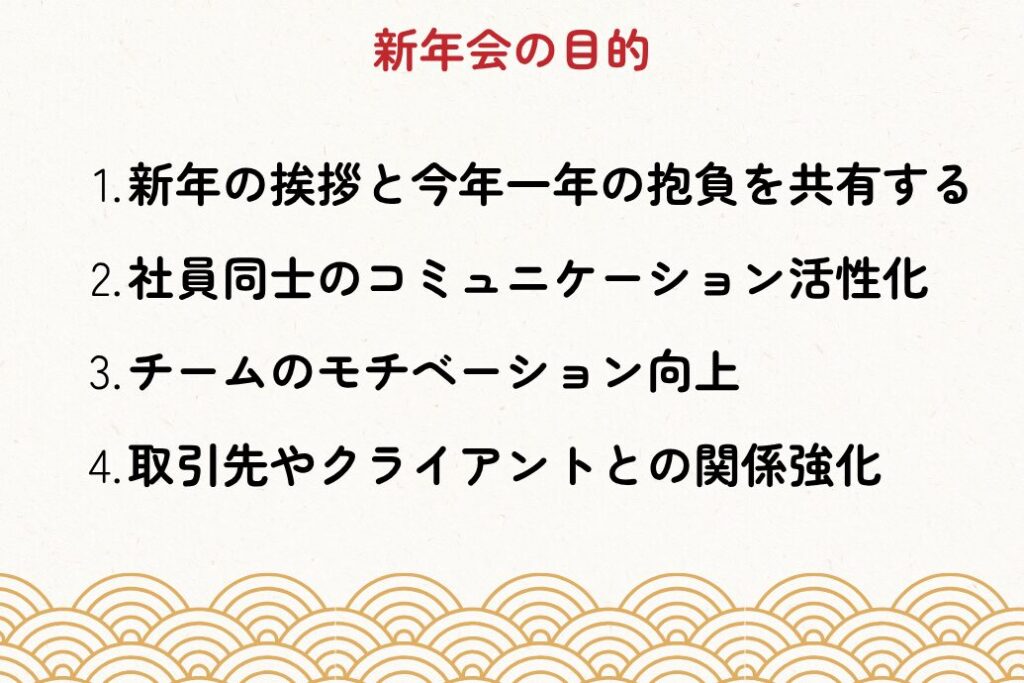
新年会を成功させるためには、まず「何のために開催するのか」という目的を明確にすることが重要です。
- 新年の挨拶と今年一年の抱負を共有する
- 社員同士のコミュニケーション活性化と絆を深める
- チームの一体感を高め、モチベーションを向上させる
- 取引先やクライアントとの関係強化
目的①:新年の挨拶と今年一年の抱負を共有する
新年会の最も基本的な目的は、組織全体で新年の挨拶を交わし、今年一年の抱負や目標を共有すること。経営層からは会社の方針やビジョンを、社員からは個人やチームの目標を語る場となります。
特に経営者や役員からのメッセージは、社員のモチベーションを左右する重要な要素。新年会という場で直接語りかけることで、文書やメールでは伝わりにくいニュアンスや熱意を届けることができます。
目的②:社員同士のコミュニケーション活性化と絆を深める
日常業務の中では「自分の部署やチームのメンバーとしか話す機会がない」という社員も多いのではないでしょうか。新年会は、普段接点のない社員同士が交流できる貴重な機会となります。
特に全社員が500名を超えるような中規模以上の企業では、同じ会社にいながらも顔と名前が一致しない、という状況も珍しくありません。新年会で直接顔を合わせて会話することで、その後の業務上のコミュニケーションを円滑にする効果があります。
目的③:チームの一体感を高め、モチベーションを向上させる
新年会は、組織全体の一体感を醸成する絶好の機会です。「同じ会社で働く仲間」という意識を再確認することで、チームとしての結束力が高まります。
特に年末年始の休暇を経て、気持ちが少し緩んでいる時期に開催される新年会は、社員のスイッチを「仕事モード」に切り替える役割も果たします。楽しい時間を共有しながらも、「今年も一緒に頑張ろう」という前向きな気持ちを喚起できるのです。
目的④:取引先やクライアントとの関係強化
社内の親睦だけでなく、取引先やクライアントとの関係強化を目的に新年会を開催する企業もあります。日頃お世話になっている方々に感謝を伝え、今年もより良い関係を築いていきたいという意思表示の場となるのです。
新年会の開催時期はいつ?適切なタイミングを解説
新年会の成功には、開催時期の選定が重要な要素となります。
一般的な開催時期は1月上旬〜2月上旬

新年会は、その名の通り「新年を祝う会」。基本的には年が明けてから開催されます。
最も一般的な開催時期は1月上旬から2月上旬にかけてです。特に多いのは1月中の開催です。まだ新年の雰囲気が残っているこの時期は、社員も「今年一年頑張ろう」という気持ちが高まっており、新年会の趣旨にも合致します。
仕事始めから1週間以内に開催するケースが多い
最も多いパターンは、仕事始めから1週間以内。つまり1月の第1週から第2週にかけての開催です。
このタイミングで行われる新年会には複数のメリットがあります。社員全員がまだ新年の挨拶モードにあるため、「新年会」という行事が自然に受け入れられます。また、年末年始の休暇で休養を取った直後であるため、社員の体調も良好な時期です。
松の内(元旦から1月7日まで)を避ける場合もある
「松の内」とは、お正月の松飾りを飾っておく期間のことで、一般的には1月7日までを指します。
企業によっては、この松の内の期間中は新年会を避け、松の内が明けてから開催するケースも。ただし、松の内を気にするかどうかは企業文化によって異なりますので、自社の雰囲気に合わせて判断すると良いでしょう。
開催時期を決める際の注意点
新年会の日程を決める際には、いくつかの重要な注意点があります。
年末年始の休暇明けのスケジュールに配慮する
年末年始の休暇明けは、多くの企業で業務が立て込む時期。休暇中に溜まったメールやタスクの処理、年始の挨拶回り、新年度の計画立案など、やるべきことが山積みになっている社員も多いでしょう。
新年会の日程を決める際には、各部署の繁忙状況を事前にヒアリングすることが重要です。
決算期や繁忙期を避ける
業種によっては、1月や2月が決算期や繁忙期にあたることがあります。自社の業務サイクルを考慮し、比較的余裕のある時期を選ぶことが大切です。
もし1〜2月が難しい場合は、「新春の会」という名目で3月に開催することも一つの選択肢となります。
取引先を招く場合は先方の都合も確認する
新年会に取引先やクライアントを招待する場合は、自社の都合だけでなく、先方のスケジュールも考慮する必要があります。重要な取引先を招く場合は、正式な招待状を送る前に、電話などで先方の予定を確認しておくことをおすすめします。
令和の今、「ランチ新年会」も急増中
2026年、新年会の新トレンドとして、「ランチ新年会」に注目が集まっています。ランチ新年会は、働き方が多様化した現代にぴったりの新年会スタイルです。
ランチ新年会とは、その名の通り、ランチタイムに行う新年会のこと。夜ではなく昼間に実施することで、社員の参加ハードルが大幅に下がり、予算も半分以下に。1時間程度で完結するため業務への影響も最小限です。また、アルハラや健康志向などの理由から、「飲みたくない社員」への配慮もなされており、社員からも喜ばれています。
実施方法や成功のポイントは以下の記事で詳しく解説しています。
新年会の開催形式と規模
新年会は、その目的や参加者によって、さまざまな形式と規模で開催されます。
社内のみで開催する新年会
最も一般的なのは、社内の社員のみで開催する新年会です。
全社員参加型の新年会
全社員が一堂に会する新年会は、組織全体の一体感を醸成する絶好の機会です。
特に中小企業や、従業員数が100名程度までの企業では、全社員参加型の新年会が開催されることが多いですね。普段接点のない部署の社員とも顔を合わせられることが大きなメリットです。
部署単位・チーム単位の新年会
従業員数が多い企業では、全社一斉ではなく部署単位やチーム単位で新年会を開催することも。参加者同士の距離が近いため、よりリラックスした雰囲気で開催でき、部署特有の話題で盛り上がれるという利点があります。
社外の方を招く新年会
新年会に取引先やクライアントなど、社外の方を招待するケースもあります。
取引先を招いた新年会
日頃お世話になっている取引先を招いての新年会は、感謝の気持ちを伝え、今年も良好な関係を築いていきたいという意思表示の場。会場や料理のグレード、プログラム内容などに、より一層の配慮が必要です。
賀詞交換会としての新年会
より フォーマルな形式として、賀詞交換会を兼ねた新年会もあります。名刺交換やビジネスマッチングの機会としても機能し、新しいビジネスの可能性が広がることもあるでしょう。
開催規模による違い
新年会の規模によって、準備すべき内容や当日の運営方法も変わってきます。ここでは、それぞれの規模における特徴と注意点を見ていきましょう。
小規模(〜30名)の新年会
参加者が30名程度までの小規模な新年会は、アットホームな雰囲気が特徴。会場は個室のある居酒屋やレストランが適しており、着席形式で落ち着いて食事を楽しめます。プログラムも堅苦しくせず、歓談の時間をたっぷりと取ることがおすすめです。
中規模(30〜100名)の新年会
多くの企業で最も一般的な規模です。宴会場やイベントスペースで、立食形式のビュッフェスタイルが人気です。ビンゴ大会や抽選会など、参加者全員が楽しめる企画を取り入れると盛り上がります。
大規模(100名以上)の新年会
ホテルの大宴会場や大型イベントスペースでの開催となります。司会者を立てた進行がほぼ必須で、音響・照明設備も重要になります。準備や運営には相当な労力が必要となるため、イベント会社への外注も検討すると良いでしょう。
新年会の主催者・幹事の役割とは
新年会を成功させるためには、主催者や幹事の役割を明確にすることが重要です。
新年会の主催者は誰が務める?
新年会の主催者は、基本的には会社や団体そのもの。実務的には、経営企画室、総務部、人事部などが幹事を務めるケースが多いですね。会社の規模や新年会の目的によっては、社長や役員が直接発起人となることもあります。
幹事が担うべき主な業務
幹事の役割は多岐にわたります。主な業務内容を理解し、計画的に準備を進めましょう。
企画立案と予算管理
まず最初に行うべきは、新年会の企画立案。開催目的、参加者の範囲、規模、予算などの基本方針を決定します。予算については、会社からの支出なのか、会費制にするのかを明確にし、料理や会場、余興などの費用配分を検討します。
会場選定と予約
参加人数や予算に応じて、適切な会場を選定します。人気の会場は早めに予約が埋まってしまうため、開催日の2〜3ヶ月前には予約を済ませておくことが理想的です。
参加者への案内と出欠管理
招待状やメールで参加者に案内を送り、出欠の確認を行います。締め切りを設定し、確実に人数を把握することが重要です。
当日の進行管理
当日は、受付、プログラムの進行、トラブル対応など、さまざまな業務が発生します。複数名で役割分担し、スムーズな運営を心がけましょう。
新年会の会場選びのポイント

会場選びは、新年会の成否を左右する重要な要素です。
会場の種類と特徴
新年会の会場には、いくつかの選択肢があります。それぞれの特徴を理解して、自社に合った会場を選びましょう。
社内(会議室・オフィススペース)で開催
社内で開催する最大のメリットは、コストを抑えられることと、移動の手間がないことです。ただし、料理やドリンクの手配が必要になるため、ケータリングサービスの利用を検討すると良いでしょう。
居酒屋・レストランで開催
小〜中規模の新年会に最適。料理やドリンクの手配が不要で、幹事の負担が軽減されます。個室があるお店を選ぶと、周囲を気にせず楽しめます。
ホテル・宴会場で開催
格式の高い新年会や、取引先を招く場合に適しています。サービスの質が高く、料理もワンランク上のものを提供できるでしょう。
イベントスペースで開催
大規模な新年会に最適。自由度が高く、レイアウトやプログラムを柔軟に設定できます。ただし、料理は別途ケータリングで手配する必要があります。
会場選びで確認すべきポイント
会場を選ぶ際には、以下のポイントを必ず確認しましょう。
収容人数とレイアウト
参加予定人数に対して、十分な広さがあるかを確認します。立食形式なら1人あたり1.5〜2平米、着席形式なら2.5〜3平米が目安です。
アクセスの良さ
駅から近い、主要な交通機関からアクセスしやすいなど、参加者にとって行きやすい場所を選ぶことが重要です。
料理・ドリンクの提供方法
料理やドリンクの提供方法、メニュー内容、追加オーダーの可否などを事前に確認しておきましょう。
新年会のプログラム例と進行のコツ
新年会を盛り上げるためには、適切なプログラム構成が欠かせません。
基本的な新年会のプログラム構成
一般的な新年会のプログラムの流れをご紹介します。この基本構成をベースに、自社に合わせてアレンジしてみてください。
開会の挨拶
社長や役員による開会の挨拶で、新年会がスタートします。今年の目標や方針を簡潔に伝えることが多いです。
乾杯
来賓や役員による乾杯の発声で、食事と歓談の時間が始まります。
歓談・食事タイム
参加者が自由に食事を楽しみ、交流する時間。全体の半分以上をこの時間に充てるのが一般的です。
余興・レクリエーション
ビンゴ大会や抽選会など、参加者全員が楽しめる企画を入れると盛り上がります。
締めの挨拶・一本締め
最後に締めの挨拶と一本締めで、新年会を締めくくります。
新年会を盛り上げる企画アイデア
新年会をより楽しいものにするための企画アイデアをいくつかご紹介します。
今年の目標発表タイム
各部署やチームから、今年の目標を発表してもらう時間を設けるのも良いでしょう。他部署の取り組みを知ることができ、組織全体の方向性が共有できます。
新年ビンゴ大会
景品付きのビンゴ大会は、定番ながら盛り上がる企画です。豪華景品を用意することで、参加者の期待感も高まります。
抽選会・豪華景品の用意
旅行券や家電製品など、魅力的な景品を用意した抽選会も人気です。社員への還元という意味でも効果的です。
新年会の料理・ドリンク選びのポイント
新年会の料理は、参加者の満足度を大きく左右する重要な要素です。
新年会にふさわしい料理とは
新年会という特別な機会にふさわしい料理を選ぶことで、参加者の満足度が高まります。
縁起の良い食材を取り入れる
新年会では、縁起の良い食材を取り入れると季節感が出ます。海老(長寿)、鯛(めでたい)、数の子(子孫繁栄)など、お正月らしい食材を料理に加えると、新年会の雰囲気がより一層高まるでしょう。
立食スタイルか着席スタイルか
参加人数や会場の広さによって、立食スタイルか着席スタイルかを選択しましょう。立食の方が参加者の移動が自由で交流しやすい一方、着席の方が落ち着いて食事を楽しめます。
ケータリングサービスの活用がおすすめの理由
新年会の料理手配には、ケータリングサービスの活用がおすすめです。特に社内や イベントスペースで開催する場合、ケータリングは強い味方となります。
幹事の負担を大幅に軽減できる
料理の準備や配膳、後片付けまでをプロに任せられるため、幹事の負担が大幅に軽減されます。当日は進行管理に集中できますね。
豪華で見栄えの良い料理を提供できる
ケータリングサービスでは、プロのシェフが手がけた本格的な料理を提供可能。見た目も華やかで、参加者に「特別感」を演出できます。
NEO DINING.のケータリングサービスの特徴
当社が運営する「NEO DINING.」では、法人・団体様向けの新年会ケータリングを展開。ミシュランで星を獲得したシェフ監修のプランから、カジュアルなプランまで、25プラン以上/100種類以上の豊富なメニューをご用意しています。
大使館や大手上場企業など、累計10,000件以上の実績がございますので、安心してお任せください。
新年会の予算と会費について
新年会を企画する際、予算設定は避けて通れない重要な要素です。
新年会の一般的な予算相場
新年会の一人あたりの予算相場は、開催形式や会場によって異なります。
社内で開催する場合は3,000円〜5,000円程度、居酒屋やレストランでは4,000円〜6,000円程度、ホテルや宴会場では6,000円〜10,000円程度が一般的な目安となるでしょう。
会費制にするか、会社負担にするか
新年会を会費制にするか、全額会社負担にするかは、企業の方針によって異なります。多くの企業では、全額または大部分を会社が負担し、社員への福利厚生の一環として位置づけていますので、会費を徴収する場合でも、一人2,000円〜3,000円程度の一部負担とするケースが多いですね。
予算内で満足度の高い新年会を実現するコツ
限られた予算の中でも、工夫次第で満足度の高い新年会を実現できます。料理のグレードを上げる代わりに会場費を抑える、または景品の数を絞って一つあたりの価値を上げるなど、メリハリをつけた予算配分が効果的です。
新年会開催時の注意点とマナー
新年会を開催する際には、参加者への配慮や安全面での注意が必要です。
参加者への配慮事項
全ての参加者が快適に過ごせるよう、以下の点に配慮しましょう。
アルコールが苦手な方への配慮
アルコールを飲めない、または飲まない方のために、ソフトドリンクやノンアルコール飲料を十分に用意しておくことが大切です。
食物アレルギーへの対応
参加者に事前にアレルギーの有無を確認し、該当者がいる場合は会場や料理提供者に必ず伝えましょう。
ハラスメント防止の観点
新年会という場でも、ハラスメント防止の意識は重要です。お酒が入る場だからこそ、節度ある言動を心がけるよう、事前に参加者に呼びかけることも検討しましょう。
感染症対策や安全面の配慮
時期や状況に応じて、適切な感染症対策を講じることも重要です。会場の換気、消毒液の設置、適切な人数制限などを検討しましょう。
新年会の企画・運営をプロに任せるメリット
大規模な新年会や、重要な取引先を招く新年会の場合、プロのイベント会社に企画・運営を依頼することも選択肢の一つです。
イベント会社に外注するメリット
イベント会社に依頼することで、さまざまなメリットが得られます。
幹事の負担を大幅に削減できる
会場選定から当日の運営まで、全てをプロに任せられるため、幹事の負担が大幅に軽減されます。本来の業務に集中できるのは大きなメリットですね。
プロのノウハウで満足度の高い会を実現
豊富な経験とノウハウを持つプロが企画するため、参加者の満足度が高い新年会を実現可能。効果的な演出や盛り上がる企画など、素人では思いつかないアイデアも提案してもらえます。
トラブル対応もスムーズ
当日、予期せぬトラブルが発生した場合も、経験豊富なプロが迅速に対応してくれるため安心です。
NEO FLAG.なら新年会もプロデュースOK
当社「NEO FLAG.」では、新年会をはじめとする社内イベントの企画・運営を全面的にサポートしています。
オンライン・オフライン・ハイブリッド形式など、あらゆる形式に対応可能です。会場選定、プログラム企画、ケータリング手配、当日の運営まで、ワンストップでお任せいただけます。
累計10,000件以上の実績を持つ当社だからこそできる、質の高い新年会プロデュースをご提供いたしますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
まとめ:新年会で良いスタートを切ろう
新年会は、単なる飲み会ではなく、組織の一体感を高め、新しい年の目標を共有する大切な機会です。開催時期や形式、プログラム内容など、考えるべきポイントは多岐にわたりますが、本記事でご紹介した内容を参考に、自社に合った新年会を企画してみてください。
幹事の負担を軽減したい場合や、より質の高い新年会を実現したい場合は、ケータリングサービスやイベントプロデュースのプロに相談することもおすすめです。NEO FLAG.では、新年会の企画から運営まで、トータルでサポートいたします。
今年の新年会を成功させて、組織全体で素晴らしい一年のスタートを切りましょう!
【ダウンロードOK】社内イベントやコミュニケーション活性化に役立つ資料も無料配布!
以下のページでは、コロナ禍の社内イベントや社内コミュニケーション活性化に役立つPDF資料を配布中です。すべてダウンロードは無料です(内容の改ざん、二次配布は禁止とさせていただきます)
「社内イベント事例集40」にて社内イベントを実施した40社の口コミや開催形式をご紹介★
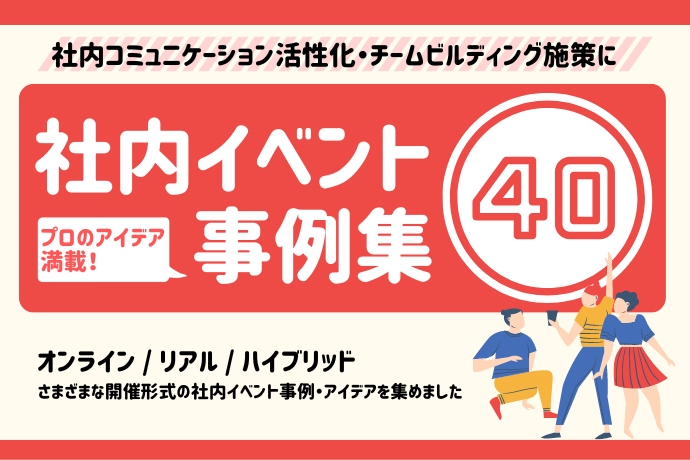
当社は、料理・イベント企画等でさまざまな形式の社内イベントに携わってまいりました。その数はオンライン・オフライン合わせて10000社以上に上ります(2022年7月現在)
本資料では、これまでに当社をご利用くださった法人・団体様の事例を40社分ピックアップしてご紹介。リアルな口コミや活用ポイントなどを、会の形式から探すことができます。
オンライン懇親会・オンラインイベントについて詳しく知りたい方は「デリマガ」もチェック
NEO FLAG.のサービス
- オンライン懇親会向け料理宅配 DeliPa(デリパ):https://delipacool.neodining-catering.com/
- オンライン懇親会用MC付き料理宅配 Parti(パルティ):https://delivery-p2.neodining-catering.com/
- 会議室懇親会 DeliPa BIZ(デリパビズ):https://delivery-p4.neodining-catering.com/
- ケータリング宅配のNEO DINING.:https://party.neodining-catering.com/
- オードブル宅配のNEO DINING.:https://delivery.neodining-catering.com/
- イベントプロデュースのNEO FLAG.:https://event.neo-flag.com/
- NEO FLAG.のハイブリッド型懇親会:https://delivery-p3.neodining-catering.com/